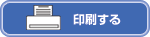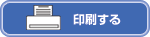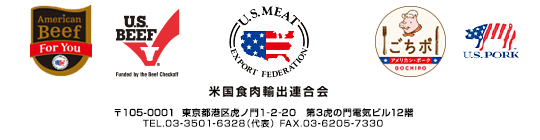|
ラボバンク社のレポートによると、乳用母牛と肉用雄牛を交配させる手法(ビーフ・オン・デイリー)が、世界の牛肉サプライチェーンにおいて重要性を増しているという。
同社のレポート「Beefing up global dairy with dairy-beef」では、この手法が注目を集める要因を世界的な視点から分析し、地域ごとの異なるアプローチを紹介している。
ラボバンクのアナリストは、「世界的なタンパク需要への対応、動物倫理への注目の高まり、気候変動対策という三つの要請に同時に応える解決策として台頭している。酪農システムに肉牛生産を戦略的に組み込むことは、もはや不可欠な手法となりつつある」と述べている。
報告書は、この交配手法の増加の背景として、牛肉価格の上昇や「社会的許容圧」と呼ぶ要因を挙げている。この手法によって未活用の子牛を減らし、ライフサイクルの効率を向上させることが、業界のイメージや持続可能性を強化することにつながるからだ。
2000年代には、米国の肥育場における肥育用去勢牛・未経産牛のうち、肉用乳牛は300万〜330万頭だった。しかし繁殖戦略と子牛供給の変化によって、2020年以降は30%以上増加し、現在では約440万頭に達しているという。
米国ではビーフ・オン・デイリーの生産がビジネス水準に達しつつあることから、乳用交雑牛の価格水準は、米国が事実上のベンチマークを形成している。アイルランドやその他の地域では、肉用乳牛は新たな選択肢として台頭している。アイルランドでは、国全体の乳牛群の拡大を背景に、牛肉生産を乳業システムに統合するための戦略が進められている。
レポートでは、NZや豪州などでも肥育および処理能力に対する圧力が高まる可能性があるとし、その実現にはフィードロット施設、仕上げシステム、食肉加工場などのインフラへの投資が重要になると指摘している。
|